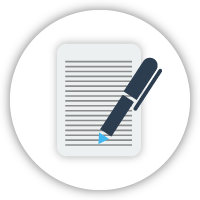論文執筆における不正行為は、研究者としての信頼を一瞬で失わせる重大な問題です。一度でも不正行為が発覚すると、論文の撤回や研究資金の返還、さらには研究機関からの解雇など、厳しい処罰が科されることがあります。また研究者本人のみならず論文を掲載したジャーナル、ひいては学術界全体の信頼にも悪影響を与えてしまいます。
まずは論文執筆における不正行為とは何か、見ていきましょう。
論文執筆における3大不正とは
文部科学省によると、一般的に論文執筆における不正行為は主に3つで、それぞれは下記のように定義されています。
捏造:
論文執筆における「捏造」とは、存在しないデータや研究結果を意図的に作成し、それを実際の研究成果として発表する行為を指します。例として、実際には行っていない実験データのでっち上げや、架空のアンケート結果の作成などが含まれます。捏造は研究の信頼性を大きく損なうため、厳しく禁止されています。研究者としての倫理を守り、正確で誠実な研究活動を行うことが大切です。
改ざん:
論文執筆における「改ざん」とは、研究資料やデータ、研究過程、研究結果などを意図的に変更し、真実でないものに加工する行為を指します。具体的にはデータの一部を削除したり、数値の変更、画像の加工などが含まれます。改ざんは、研究の信頼性を損なうだけでなく、他の研究者や社会全体に対しても大きな影響を与えます。例えば、改ざんされたデータに基づいて行われた研究は再現性がなく、科学的な進歩を妨げる可能性があります。改ざんを防ぐためには、研究データの適切な管理や、第三者によるデータの検証が必要です。
盗用:
論文執筆における「盗用」とは、他人の研究成果やアイデアを適切な引用や許可なしに自分のものとして発表する行為を指します。例えば、他人の文章やデータを黙って使用してしまう、また他人のアイデアを自分のものとして発表することなどが含まれます。
ジャーナルが不正行為に対して取るべき対応
不正行為を見抜けずに不正論文をジャーナルに掲載してしまい、その後適切な対応がとれないと、きちんと査読をしていないのではないか、運営体制に問題があるのではないかと疑われ、ジャーナルの信用が失墜してしまう可能性があります。そのため学術出版における倫理的なガイドラインを提供しているCOPEの指針に準拠したジャーナル運営を行うことが重要になります。また「盗用」を未然に不正を防ぐために剽窃チェックツールの導入も大変効果的です。
COPE(出版倫理委員会)
COPEは、学術出版における倫理的な問題に対処するためのガイドラインを提供する国際的な非営利団体です。不正行為が発覚した場合には迅速かつ適切な対応が求められますが、COPEにはそのためのガイドラインやフローチャートが整備されています。
倫理的な問題が発生した場合に、COPEのガイドラインを参照することでジャーナルとして適切な対応をとることができます。
剽窃チェックツール
原稿中の文章と出版済みの文献などの文章を比較し、類似度を評価するツールです。投稿受付時に利用されることが多く、類似度が高い場合には著者への確認や即時リジェクトの対象とすることもあります。
剽窃チェックツールを利用することで、盗用のリスクがある論文を検出できます。
例) Similarity Check、iThenticate
適切な対策を講じないと、知らず知らずのうちに大きな問題に発展する可能性があります。論文不正が発生した際の対処法や、その未然防止策について興味をお持ちの方は、ぜひSeeklまでご連絡ください。
※参考 文部科学省:研究活動の不正行為等の定義
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/attach/1334660.htm