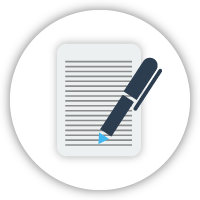著者としてジャーナルに論文が掲載される、ということは、具体的に何を意味するのでしょうか。それは研究実績となり、学術的・社会的な権利や責任、そして信用をもたらします。しかし、研究に参加した人は誰でも著者として認められるわけではありません。それでは、何をしていれば著者を名乗ることができるのでしょうか。
1. 著者資格をどう捉えるか
論文を書いた人が著者である、というのは、簡単明瞭な事実に思われますが、そうシンプルにはいかないのが現実です。著者資格を巡って争いが起きた事例を、COPE(Committee of Publication Ethics)のサイトから引用してみます。
ある著者Xが執筆した論文について、研究に不可欠な調査を行ったYを著者に含めるかどうかが問題となりました。両者ともYの貢献内容については概ね合意していたものの、著者資格について異なる見解を持っていたのです。Xは単独著者での出版を主張していますが、Yは自分も著者とするよう求めており、いまだ交渉は難航しています。
この事例からは、著者資格について、共通した見解が必要であることがわかります。厳密には、著者と貢献者を区別する基準が必要です。ここからは、その基準を詳しく見ていきましょう。
2. 著者とは誰か
[著者資格について]
著者資格の定義として、最も広く受け入れられているのが、ICMJE(International Committee of Medical Journal Editors)が定める4つの基準です。
① 研究の着案や計画、あるいはそのためのデータ取得・分析・解釈への実質的な貢献
② 研究の設計、あるいは知的側面での重要な内容についての批判的なチェック
③ 投稿前の最終承認
④ 成果物の正確性または完全性に関する疑問が適切に調査・解決されることを保証する点において、著作物のすべての面について責任を負うことに同意すること
ICMJEはさらに、著者の義務をいくつか挙げています。
– 成果物全体に対して説明可能であること
– 共著者の責任箇所を把握し、その内容に偽りがないと保証できること
– 4つの基準すべてを満たしていること
つまり、著者とは、研究の全工程を通じて実質的な貢献を行っており、研究全体の責任を負い、説明ができる人であると言えます。時に多くの人が関わる研究では、様々な貢献の形がありえます。その中でも中心的な役割を担った人物を著者とし、他を貢献者として区別するのがICMJEの定めた定義です。
[複数著者]
実質的に知的な貢献をした人物が、複数人いることもあります。その場合は、誰が著者資格を持っているかの見極めが重要になります。以下のような観点が挙げられるでしょう。
– 全員が4つの基準を満たしていること
– 全メンバーの取り組み内容が、正確で誠実であると保証できること
ジャーナルによっては、各著者が具体的にどう貢献したかについて、明示することを求めるものもあります。貢献内容の分類方法には、論文への著者の貢献度を具体的に示すための基準であるCRediT(Contributor Roles Taxonomy)が広く用いられています。
[不正から見る著者資格]
著者を巡る不正としては、代表的なものに以下があります。
– ギフト・オーサーシップ:研究に貢献していない者を著者とすること。研究業績の水増しや、機関の長への誤った謝意の表し方として行われることが多い。
– ゴースト・オーサーシップ:研究に貢献した者を著者としないこと。利益相反の隠蔽に使われることが多い。
このような不正があるからこそ、実質的な貢献と責任を要求する著者資格の基準が重要になるのですね。
3. AIは著者か?
多くの分野でAIの実用化が進んでおり、研究においても、データの分析や執筆補助などの活用方法が存在します。AIが大きな助けとなりうることは事実ですが、AIを著者名に連ねることは適切なのでしょうか?
結論としては、ChatGPT等チャットボットをはじめとするAIを、著者として考えるべきではありません。なぜならAIはICMJEが定義する著者の条件の4つ目「成果物の正確性または完全性に関する疑問が適切に調査・解決されることを保証する点において、著作物のすべての面について責任を負うことに同意すること」を満たせないためです。AIは成果物に対して責任を持てず、説明もできませんが、それこそが著者資格に必要なものなのです。
AI技術を補助として使用した場合は、MethodsやAcknowledgementに記載することが適切でしょう。すでにルール化しているジャーナルもあるので、投稿規程をよく確認することをお勧めします。
4. まとめ
著者資格は一筋縄ではいかない問題ですが、避けて通ることはできません。意図せぬトラブルを避けるためにも、投稿先ジャーナルの投稿規程をよく確認し、適切な人物のみを著者として掲載するよう注意しましょう。
またジャーナル側として著者リストに違和感を覚えた場合は必ず投稿者に確認し、不正が疑われる論文を審査対象から除くこと、問題のある論文を掲載してしまった場合に備えることも必要です。そのためにもジャーナルを最新の国際基準に合わせてアップデートし続けましょう。お困りの場合は、ぜひSeeklにお問い合わせください。
参考資料
- COPE (Committee on Publication Ethics). Discussion Document: Authorship. 2019
- COPE (Committee on Publication Ethics). What contributes authorship? 2010
- ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors). Recommendations. Defining the Role of Authors and Contributors. 2025
- NISO. Contributor Role Taxonomy (CRediT). 2022