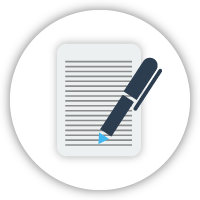デジャヴ(既視感)は、時として初めて見るものに対しても抱くことがありますが、論文に対してデジャヴを感じたなら、注意が必要です。出版済みの論文を、引用や参照なしに再度出版されていれば、それは重複出版になります。以前、こちらのコラムで論文執筆における3大不正行為についてご紹介しましたが、今回は不正行為の中でも重複出版に絞り、事例を確認していきましょう。
重複出版とは
まず、重複出版はどのように定義されるのでしょうか。多くの生物医学雑誌で採用されている、国際医学雑誌編集者委員会(ICMJE)の方針における説明を見てみましょう。
すでに掲載された論文と内容が大幅に重複する論文を、過去の論文について明確に言及することなく掲載すること。
さらに、ICMJEには、ジャーナルの読者にとって、読んでいる論文がオリジナルだと信じられることは当然の権利だとも書かれています。
重複出版の問題点
では、重複出版は具体的にどんな問題を引き起こすのでしょうか。
著作権
許可を取り適切に引用を示していれば問題ありませんが、重複出版においては先の出版物の著作権を侵害することがあります。特に論文の著作権がジャーナルに属している場合は、ジャーナル間での争いに発展する可能性もあるでしょう。
資源の有効利用
論文が投稿されてから出版に至るまで、編集や査読には大きなリソースが割かれます。重複出版によって、ひとつの論文に対して2倍のリソースが費やされることになります。重複出版発覚時の対応も含めると、軽視できない量のリソースが無駄遣いされることとなってしまいます。
既存エビデンスの歪曲
同一のデータを二重カウントしてしまったり、結果が不適切に重視されたりすることで、該当分野における実証を歪曲する可能性があります。著者や編集者だけでなく、広く悪影響を及ぼす結果になってしまうのです。
複出版への対応事例
実際に重複出版が判明したら、どのように対応すべきなのでしょうか。ここからは、COPE(Committee on Publication Ethics:出版倫理委員会)に掲載されている重複出版への対応事例を見ていきましょう。
① ほぼ同一内容で共著者が異なる論文が出版されたケース
編集者は著者の出版権剥奪(=ブラックリスト追加)を検討していましたが、COPEはブラックリスト非推奨の立場を明言しました。それを受けて、著者を特別警戒対象とする「グレーリスト」への追加を検討しています。
元の記事はこちら
② 英語で出版された論文を、外国語で出版したケース
該当ジャーナルでの出版禁止に次いで、学会の別ジャーナルでも10年間出版禁止が決定しました。COPEはまず調査が必要であるとし、出版禁止を再考するよう促しています。
元の記事はこちら
③ 同一著者により同一データが使用されたケース
著者たちを3年間の投稿禁止とし、所属機関長に対して著者の行為について通知しました。COPEは不正を知らない著者がいる可能性も示唆しており、全著者を投稿禁止とすることは公平ではない見解を示しています。
元の記事はこちら
④ 論文内容の類似を著者が否定したケース
両ジャーナルの編集者と査読者は重複出版にあたると考え、2年間のブラックリスト追加を検討していました。しかしCOPEは、それは重すぎるとして3年間の査読辞退を提案しています。
元の記事はこちら
COPE委員会の方針
ケースによって対応はさまざまですが、COPEは一貫して下記のような方針を維持しており、各ジャーナルが参考とするよう奨励しています。
- 【非推奨】著者のブラックリスト掲載やその他の制裁を与えること(訴訟のリスク回避のため)
- 【推奨】特定の重複率ではなく、重複の質と程度で判断すること
- 【推奨】分野や論文種別、学生の論文でないかなどを考慮すること
重複出版をはじめ不正行為はあってはならないものですが、ジャーナルを運営する上で避けては通れないことも事実です。対応には時として慎重さも求められ、一歩誤ればジャーナルそのものの信用を揺るがしかねません。Seeklでは、国際的な学術状況に精通したコンサルタントが、各ジャーナルに合わせた最適な運営プランをご提案しております。あらゆる問題に対応し、ジャーナルの質を向上させるためのお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。