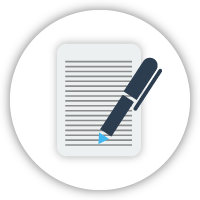「巨人の肩の上に立つ」ためには、古今東西の知の資産に触れなければなりません。これを後押しするのが、学術論文に対し、誰もがインターネットを介して無料でアクセスできるOA(オープン・アクセス)です。いまや世界的な潮流となっており、人類の知を広く共有する有益な取り組みである一方で、注意すべき動きもあります。まずはOA誕生の背景から昨今の周辺情報に至るまで、ひとつずつ見ていきましょう。
・OAの歴史と定義
今では一般的となったOAですが、そもそもどのようにして発展してきたのでしょうか?その始まりは、1990年代後半に遡ります。当時、学術論文の増加や大手商業出版社による市場寡占などにより、学術ジャーナルの価格は高騰していました。研究に必要な論文を入手できない状況に対抗運動が起こり、2002年、OAの定義として「ブダペスト・オープンアクセス・イニシアティブ」が確立されました。その定義を一言でまとめると、以下のようになるでしょう。
インターネットで記事の全文に無料でアクセスでき、利用できること。その際、金銭的、法的、技術的な障壁があってはならない。
上記の運動を発端とし、欧米を中心とした各国で公的な資金援助を受けた研究について、その成果をOAとするよう義務付ける法律が整備されていきます。代表的な動きとして、2018年に欧州の国立研究助成機関が開始したcOAlition Sによる「Plan S」があります。
・OAのビジネスモデルと種類
OA化に伴い、従来のサブスクリプション型のビジネスモデルは転換を迫られました。その結果、読者から購読料を徴収する代わりに、投稿者がAPC(論文掲載料)を支払うという仕組みが誕生しました。この仕組みにより、出版の費用が賄われ、読者は無料で論文にアクセスできるようになったのです。
OAと一口に言っても、APCの有無や公開時期・公開方法に応じて、いくつかの種類が存在します。以下に挙げた5つのうち、プラチナOAが理想的なものとされています。
プラチナOA :投稿者のAPC不要でOA
ゴールドOA :投稿者がAPC負担でOA
グリーンOA :機関リポジトリ等でのOA
ディレイドOA :論文公開から一定期間経過後にOA
ハイブリッドOA :投稿者が公開方法を選択可能。OAの場合はAPCを支払う。
・OA化のメリット
論文のOA化による最大のメリットは、言わずもがな論文への制限のないアクセスです。人類共通の知の財産として広く共有することで、分野を超えた学問の発展にもつながります。加えて、OA化には以下のような波及効果が期待できます。
- 論文が引用される可能性の増大
- 社会に対する責任説明と還元の保証
- 科学の透明性の確保
- 研究成果の相互評価による論文の質向上、研究発展の促進
OAには、読者側だけでなく投稿者側にとっても多くのメリットがあることがわかりますね。
しかし、OA化が促進されたことによる負の一面もまた存在します。それは、APC支払いの仕組みを悪用されるケースです。
・ハゲタカジャーナル
ハゲタカジャーナルとは、APCによる収益を目的とし、査読プロセス等を怠る粗悪な学術ジャーナルのことです。投稿した研究者のキャリアに悪影響があるだけでなく、学術全体に対する信頼性の脅威にもなりえます。
2025年のICMJEアップデートの際にも、ハゲタカジャーナルに関する指針が更新されました。具体的にはどのように見分けるべきか、こちらでもいくつかご紹介します。
- ジャーナルのWebサイトを確認する(査読期間が異常に短い、レイアウトが稚拙でないかなど)
- 周りの研究者の評判を聞く
- 別ジャーナルのタイトルに酷似していないか確認する
- 編集委員会のメンバーを調べる
他には、「ハゲタカジャーナルでない」とお墨付きを得ているデータベースに収載されているかどうかで調べることもできます。「ホワイトリスト」とも呼ばれ、代表的なものとしてDOAJ(Directory of Open Access Journals)が挙げられます。
・DOAJ
世界中のOAジャーナルと論文を掲載したデータベースで、言語や専門分野、地域の垣根を越えて高品質のジャーナルや論文の提供を目的としています。OAだけを対象としており、収載されるためには審査をクリアしなければなりません。収載条件を一部ご紹介します。
- ゴールドOAであること
- CCライセンス(二次利用方針)を明記していること
- ジャーナルWebサイトが適格であること
各国でOA化の方針の策定、推進が行われていますが、日本もまた例外ではありません。政府が2024年2月に発表した政策では、論文や研究データをオープンにしていく方針が掲げられました。今後もこの動きはますます強まっていくことが予想されます。
このような風潮の中で、国際的に投稿されるジャーナルとなるためにOA化を検討している、あるいは信頼できるOAジャーナルとしてのお墨付きを得るために、DOAJ収載を目指したい、こういったさまざまな課題に対し、Seeklでは万全のサポートをご用意しています。お気軽にお問い合わせください。