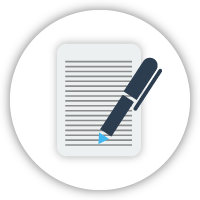研究にはお金がかかる。
程度の差はあれ、これはどの分野にも共通した事実でしょう。
研究に必要な設備や試薬はもちろん、論文を読むにも投稿するにもお金がかかります。
この研究予算、少なくともその一部は、科学研究費助成事業(科研費)を始めとした公的な資金で賄われています。わたしたちの納めた税金から生まれた研究成果は、論文として読まれることで、最終的には様々な形で社会に還元され、わたしたちの生活文化を発展させています。
「論文が読まれること」は次の研究の足掛かりを作ることであり、この循環を作り出すうえで特に重要な工程といえるでしょう。そのためには誰でも制限なく最新の論文にアクセスできる環境を整えること=即時オープンアクセス(即時OA)化が効果的と考えられています。
OAについては以前でご紹介したように購読料の高騰に対するカウンターという文脈で語られることも多いのですが、実は公的な資金、すなわち税金から生み出されたものをより社会へ還元すべしという政治的な圧力もその普及を後押ししています。
というわけで今回のSeeklコラムでは欧州、アメリカ、日本を例として「公的資金とOA義務化」について深堀していきます。
公的資金とOA出版の義務化
公的資金を受けた研究のOA出版の義務化という流れを確立させたのは、欧州の国立助成機関を中心に結成された「cOAlition S」が打ち出した「Plan S」という計画でした。
Plan Sとは
「公的助成研究から発表された成果物について完全かつ即時OAを実現する」という理念のもと、2018年に発表されました。10の原則と共に即時OA出版を実現する3つの方法(ゴールドOA、ゴールドOAへの転換ジャーナル、グリーンOA)を提唱し、大きな議論を呼びました。
彼らの投じた一石は大手出版社による寡占市場を揺らし、OA化という大きな流れを加速させた要因の一つと言えるでしょう。
アメリカにおける公的資金とOA出版
次に世界有数の論文産出国であるアメリカの動きも見てみましょう。
2013年、米国科学技術政局は大規模な助成機関に対し「資金提供を受けた研究成果は12か月以内に無料公開する計画」の策定を求めました。この時点では1年間のエンバーゴ付きOA出版が基本方針でした。
その後PlanS等の影響により国際的にOAが推進されたこと、COVID-19による騒乱をうけて即時公開の有効性が明確になったことで、アメリカも即時公開へと方針を切り替えていきます。
2022年、米国科学記述政局は全ての助成機関に対し、即座OA方針の実施計画の策定を求める通称” ネルソンメモ”と呼ばれるメモランダムを公開しました。
- 各研究助成機関の即座OA方針の実施計画は2024年末までに確定・公開され、公開の1年後までに施行される
- 査読付き研究論文:研究助成機関の指定するリポジトリを通じ、エンバーゴ無く、誰でも無償でアクセス可能とする
- 研究データ:論文の根拠データは論文の出版と同時に公開。その他の研究データは、公開方法やタイムラインを検討)
などと定められており、これによりアメリカもまた即時OAという方針へ大きくシフトすることになりました。
ちなみにもう一つの論文算出大国である中国は、国策レベルでのOA出版義務化はしていないものの、助成機関によっては義務化または推奨するというところも出てきているようです。
日本では2025年から即時OA出版が義務化
最後に国内の状況も見てみましょう。
2023年のG7広島サミット及びG7仙台科学技術大臣会合において、公的資金による研究成果への即時OAの支援を含むオープンサイエンスの推進が共同声明に盛り込まれました。そして2024年2月、内閣府は「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」を発表しました。
この基本方針の中で2025年度から新たに公募する競争的研究費の受給者に対し、研究成果物と根拠データの即時OAでの公開が義務付けられています。
ジャーナルの対応は?
欧州、アメリカ、日本と主要各国の動きを見てきましたが、2025年現在、いずれも助成の受給者に対し即時OA出版を義務化する方針へと舵を切っており、中国はOA出版義務化まではしていないものの、OAを推奨する方針をとっています。
多くの研究は公的な資金に支えられている状況を鑑みると、OA出版を推進する流れはしばらく変わらないと考えられます。
こうした状況を踏まえ、ジャーナルとしてどんな対応を取るべきでしょうか。
全てのジャーナルに共通して言えることは、セルフアーカイビング・ポリシーを定めておくことです。2025年10月現在、日本やアメリカは研究者が即時OAの義務を負い、論文や研究データは“グリーンOA”で公開することを基本方針としています。特に国内からの投稿が主なジャーナルは著者がスムーズに論文を公開できるよう、準備することをお勧めいたします。
すでにOA化済みの雑誌であれば、DOAJというデータベースへの収載がおすすめです。OA誌に付きまとう問題としてハゲタカジャーナルの存在がありますが、”信頼のできる”OA誌のデータベースであるDOAJに収載されることで、著者に大きな安心感を与えることができます。
最後に購読モデルや会員限定公開としているジャーナルについてです。Plan Sでは購読モデルを基本としたジャーナルでのOA出版(いわゆるハイブリッドOA)は認めておらず、完全OA モデルへの移行を決めているジャーナルでのみハイブリッド出版を認めています。もちろん著者がセルフアーカイブすることで回避できますが、完全OAの競合誌があればそちらに流れてしまう著者も多いことでしょう。またこれらの出版形態に比べるとOA誌の方が圧倒的に”読まれやすい”ため、引用に繋がる可能性も広まります。こうしたジャーナルではOA化自体を検討されるのも良いでしょう。
まとめると次の通りです。
- すべてのジャーナルはセルフアーカイビング・ポリシーの設定が必須
- OA誌はDOAJへの収載を目指すべし
- 購読モデル、会員限定公開のジャーナルは完全OA化も視野に
多くの研究を支える助成金、その条件としてEUに加えて日本、アメリカがOA出版を義務化しました。これに追従する国もでてくるでしょうし、今後ますますOA出版は推進されていくと予想されます。
投稿先として選ばれ続けるためにも、この大きな流れに乗り遅れないよう対応をお勧めいたします。
Seeklではオープンアクセス化やDOAJ申請もサポートしています。もしご不明な点やご不安なことがございましたら、ぜひお問い合わせください。
[参考文献]
‘Plan S’ and ‘cOAlition S’/
学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針
科学技術指標2024. 4.1.4オープンアクセス(OA)論文の動向
国立情報学研究所 オープンサイエンス基盤研究センター
OSTPによる新たなメモ:当初の感想と疑問